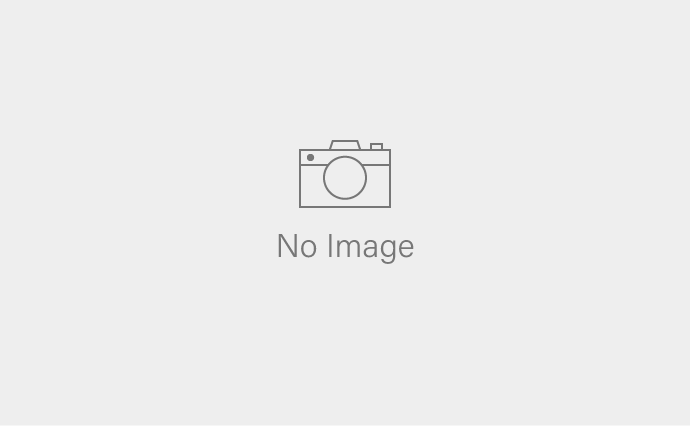ネットワークエンジニアは、ITインフラを支える重要な職種でありながら、一部では『やめとけ』という声も聞かれます。なぜこのように言われるのでしょうか?本記事では、現役エンジニアの視点から、その理由と現実をわかりやすく解説します。
1. 夜勤が多い現場がある
ネットワークエンジニアの仕事は、システムやネットワークの安定稼働を支えるため、メンテナンスや作業が業務利用時間外に行われることがよくあります。そのため、夜勤が発生するケースも少なくありません。
- システム停止を伴う作業は深夜〜早朝に行う必要がある
- 障害対応で突発的に夜間呼び出されることもある
夜勤が常態化すると、生活リズムの乱れや体調管理の難しさがストレス要因となります。
2. 土日・祝日の勤務や待機がある
24時間365日稼働するネットワーク環境では、土日祝日もシステムを監視・運用し続ける必要があります。そのため、以下のような勤務体制になることがあります:
- シフト勤務制で休日もローテーション勤務
- 障害発生時の休日呼び出し対応
予定を立てづらく、家族や友人との時間が制限されることも、『やめとけ』と言われる理由のひとつです。
3. トラブル対応のプレッシャー
ネットワーク障害が発生すると、ビジネス全体が止まるケースもあるため、エンジニアには迅速かつ的確な対応が求められます。特に大規模障害時には次のような負荷がかかります:
- プレッシャーの中で原因特定と復旧を行う必要がある
- 関係部署や顧客への報告責任が発生する
- 復旧後も再発防止策の立案と実施が求められる
精神的負担が大きく、責任の重さに悩む人もいます。
4. 常に新しい技術の勉強が必要
ネットワーク技術は進化が早く、以下のようなスキルアップが求められます:
- CiscoやFortinetなどの機器に関する知識
- 仮想化技術(例:VMware、GNS3)やクラウド(AWS、Azure)への対応
- セキュリティ技術の習得(VPN、ファイアウォール設定など)
そのため、定期的な勉強や資格取得(例:CCNA、CCNP)が欠かせません。学習時間の確保が難しい人にとっては、これも「やめとけ」と言われる一因です。
5. 在宅勤務が難しい現場も多い
近年はリモートワークが広がっていますが、ネットワークエンジニアの業務には現場対応が必要な場合が多く、在宅勤務の導入が難しい企業も存在します。
- データセンターやオフィスの機器トラブル対応
- 物理機器の設置・交換作業
- セキュリティ上、リモートからアクセスできない環境
家庭の事情や働き方を重視したい人にとっては、柔軟な働き方がしづらい点がデメリットとなるでしょう。
まとめ:本当に『やめとけ』なのか?
ネットワークエンジニアが『やめとけ』と言われる理由には、夜勤・休日出勤・トラブル対応・継続的な学習・在宅困難など、現場ならではの課題が存在します。しかし、これらは「どの職場・どのポジションに就くか」に大きく左右されます。
運用保守ではなく、設計やプリセールス、クラウド系業務にキャリアアップすれば、負担は軽減されることもあります。最も大切なのは、自分の価値観や働き方に合ったキャリアを描くことです。
ネットワークの知識は多くのIT職種に応用できる基礎力です。『やめとけ』という声に惑わされず、冷静に業界全体を見渡して判断することが重要です。